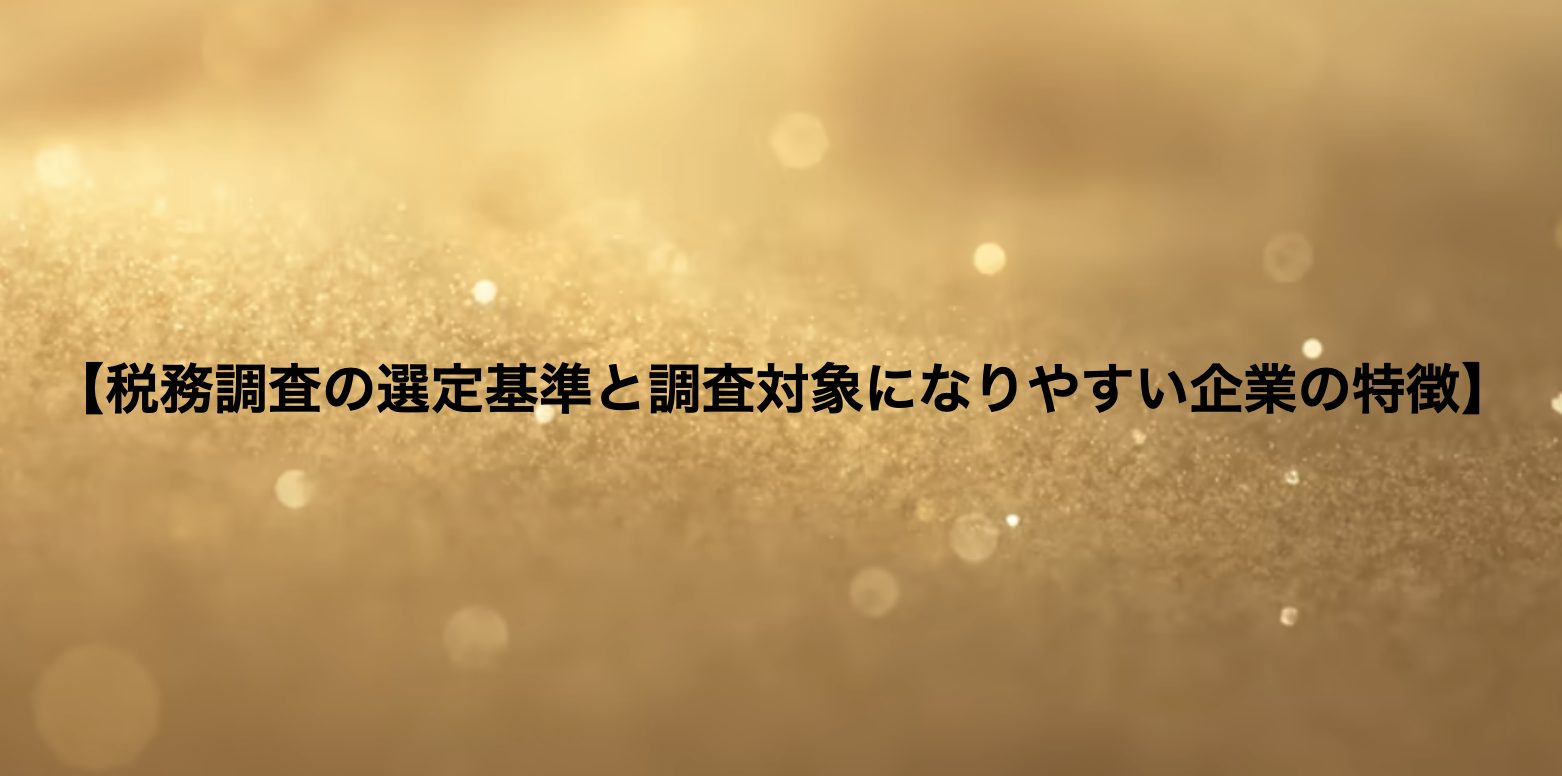
2025年7月12日
税務署はどのような基準で調査対象企業を選定しているのでしょうか。この疑問は多くの経営者様がお持ちのことと思います。調査選定の仕組みを理解することで、適切な税務管理の重要性をより深くご理解いただけるでしょう。
税務署の調査選定は、主にコンピューターシステムによる分析と税務署職員による判断の組み合わせで行われております。国税庁のKSK(国税総合管理)システムでは、申告データを基に様々な指標を計算し、異常値を示す企業を抽出しています。
具体的な選定基準として、まず業界平均との比較があります。同業他社と比較して売上総利益率や営業利益率が著しく低い場合、原価の計上や経費処理に問題がないか確認される可能性が高まります。特に製造業や小売業では、この傾向が顕著に現れます。
前年度との比較も重要な指標です。売上が大幅に増加しているにも関わらず利益が減少している、または売上は横ばいなのに経費が急増している場合などは、調査対象として注目される可能性があります。経営環境の変化を適切に説明できる資料の準備が重要です。
現金取引の多い業種は伝統的に調査対象となりやすい傾向があります。飲食業、理美容業、小売業、建設業などがこれに該当します。現金売上の計上漏れや現金経費の妥当性について、特に厳しくチェックされることが予想されます。
海外取引がある企業も調査対象になりやすい特徴の一つです。移転価格税制、外国税額控除、国際的租税回避への対応など、複雑な税務処理が必要な分野であるため、税務署も重点的に確認を行います。適切な文書化と価格設定根拠の準備が不可欠です。
関連会社間取引が多い企業も注意が必要です。特に親族間での会社間取引や、同一経営者が複数の会社を経営している場合は、取引価格の妥当性や所得の付け替えがないかを詳細に調査される傾向があります。
税務調査の頻度は業種によっても異なります。一般的に調査頻度が高いとされるのは、不動産業、建設業、医療業、飲食業などです。これらの業種では現金取引が多い、利益率のばらつきが大きい、業界特有の慣行があるなどの理由があります。
最後に、過去の調査結果も選定基準に影響します。前回の調査で重要な指摘を受けた企業は、改善状況を確認するため比較的短期間で再調査される可能性があります。逆に、適正な申告を続けている企業は調査頻度が低くなる傾向があります。
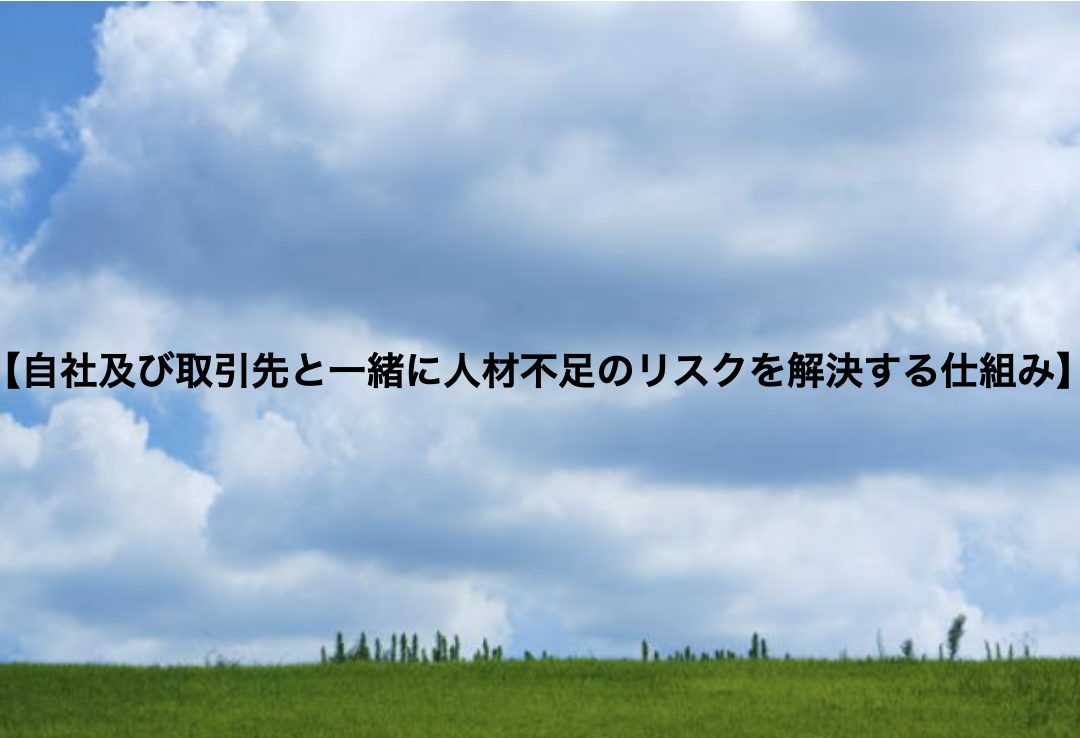




 facebook
facebook LINE
LINE Instagram
Instagram