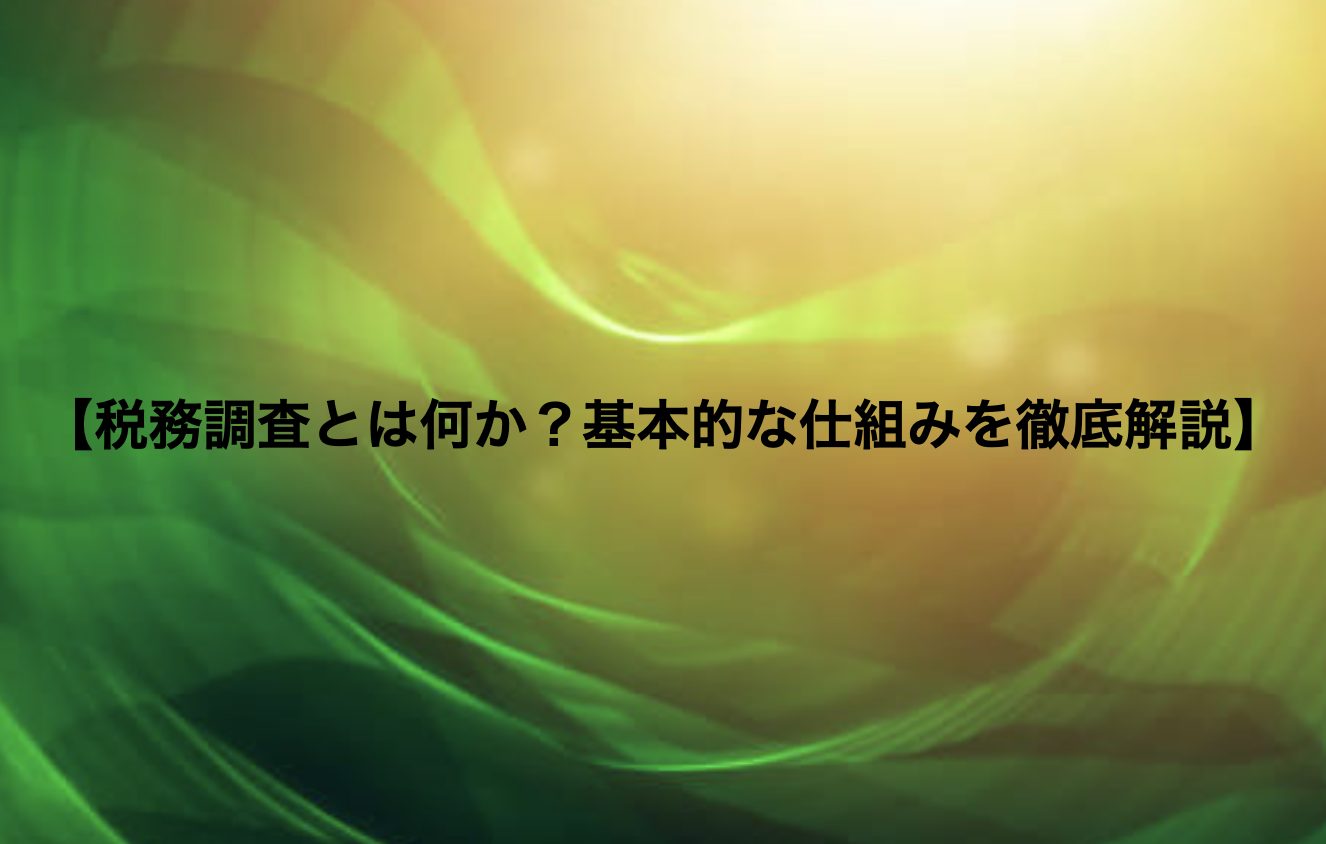
2025年7月9日
税務調査という言葉を聞くと
多くの経営者様が不安を感じられることでしょう。しかし、税務調査の基本的な仕組みを理解すれば、必要以上に恐れる必要はございません。本記事では、税務調査の基本について詳しくご説明いたします。
税務調査とは、税務署が納税者の申告内容が正しいかどうかを確認する手続きのことです。国税庁の統計によれば、法人税の実地調査件数は年間約9万件程度で、これは全法人数の約3%に相当します。つまり、確率的には決して高くないものの、いつ自社に調査が入るかは予測できないというのが実情です。
税務調査には大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類がございます。一般的に行われるのは任意調査で、これは納税者の同意を得て実施されます。強制調査(査察)は脱税の疑いが強い場合に行われる特別な調査で、マルサと呼ばれることもあります。
任意調査は事前通知が原則となっており、通常は電話で連絡が入ります。調査官は調査の目的、対象税目、対象期間、調査予定日時、場所、調査に必要な書類などを説明いたします。この時点で慌てる必要はございません。適切な準備期間を確保することが可能です。
調査の対象となりやすい企業の特徴としては、売上が急激に増加している、同業他社と比較して利益率が異常に低い、現金取引が多い、海外取引がある、関連会社間取引が多いなどが挙げられます。ただし、これらに該当するからといって必ずしも問題があるわけではありません。
税務調査で重要なのは、正確な記帳と適切な書類保存です。会計帳簿、領収書、契約書、議事録などの書類は法定保存期間中は適切に保管する必要がございます。デジタル化が進む現代においても、原本の保存は重要な意味を持ちます。
調査結果によって追徴税額が発生する場合もございますが、これは必ずしも悪意のある脱税を意味するものではありません。複雑な税法の解釈の違いや、単純な計算ミスが原因の場合も多くございます。重要なのは、調査に対して誠実に対応することです。
近年、税務調査はより効率的になっており、事前に企業の情報を詳細に分析してから実施されることが多くなっています。そのため、日頃からの適切な税務処理と記録保持が重要性を増しています。専門家である税理士との連携も欠かせません。
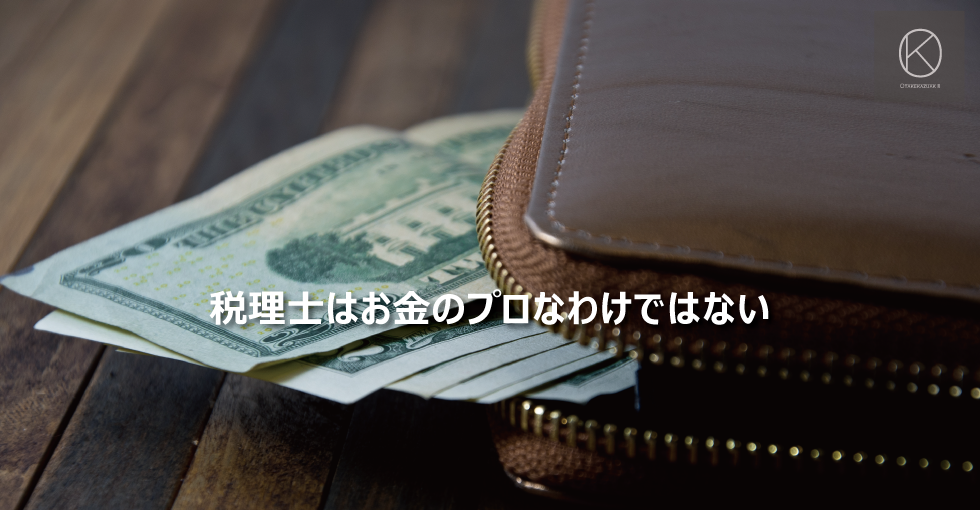
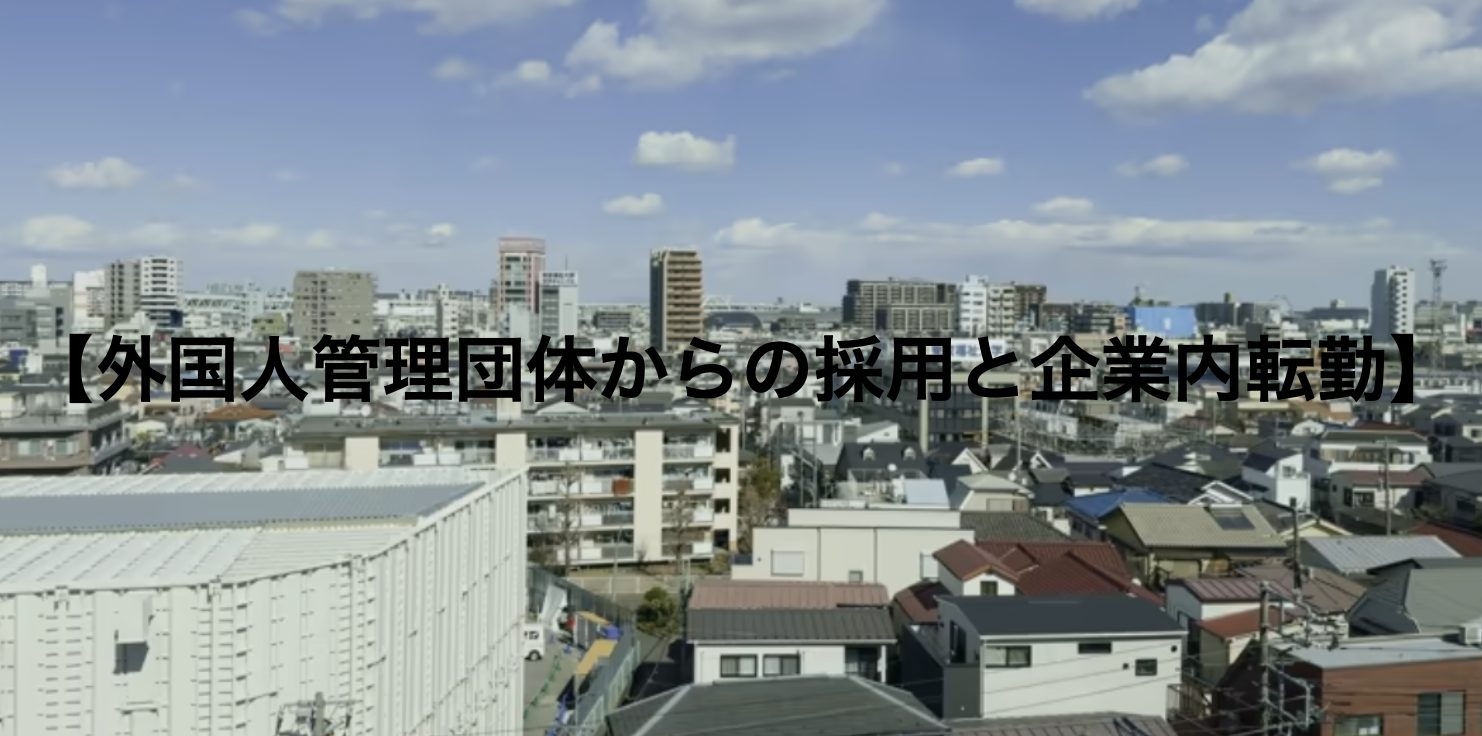
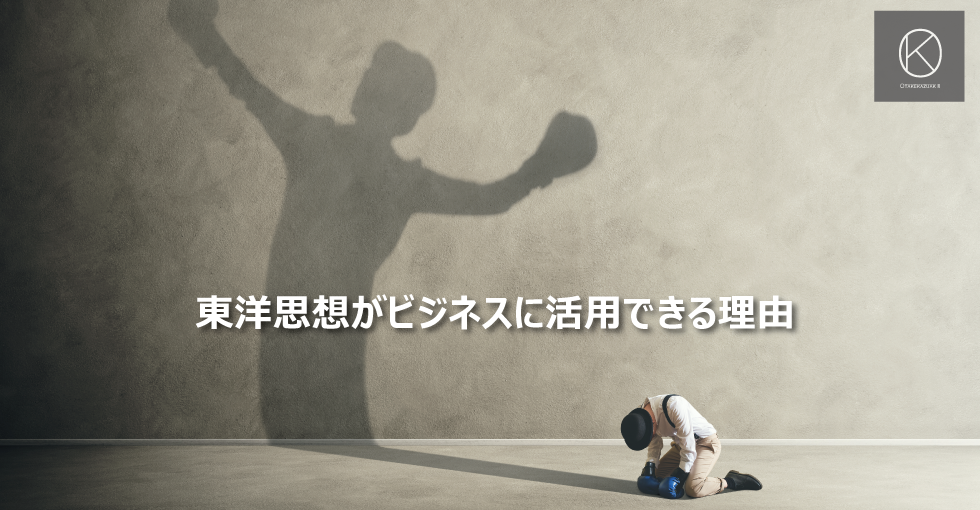
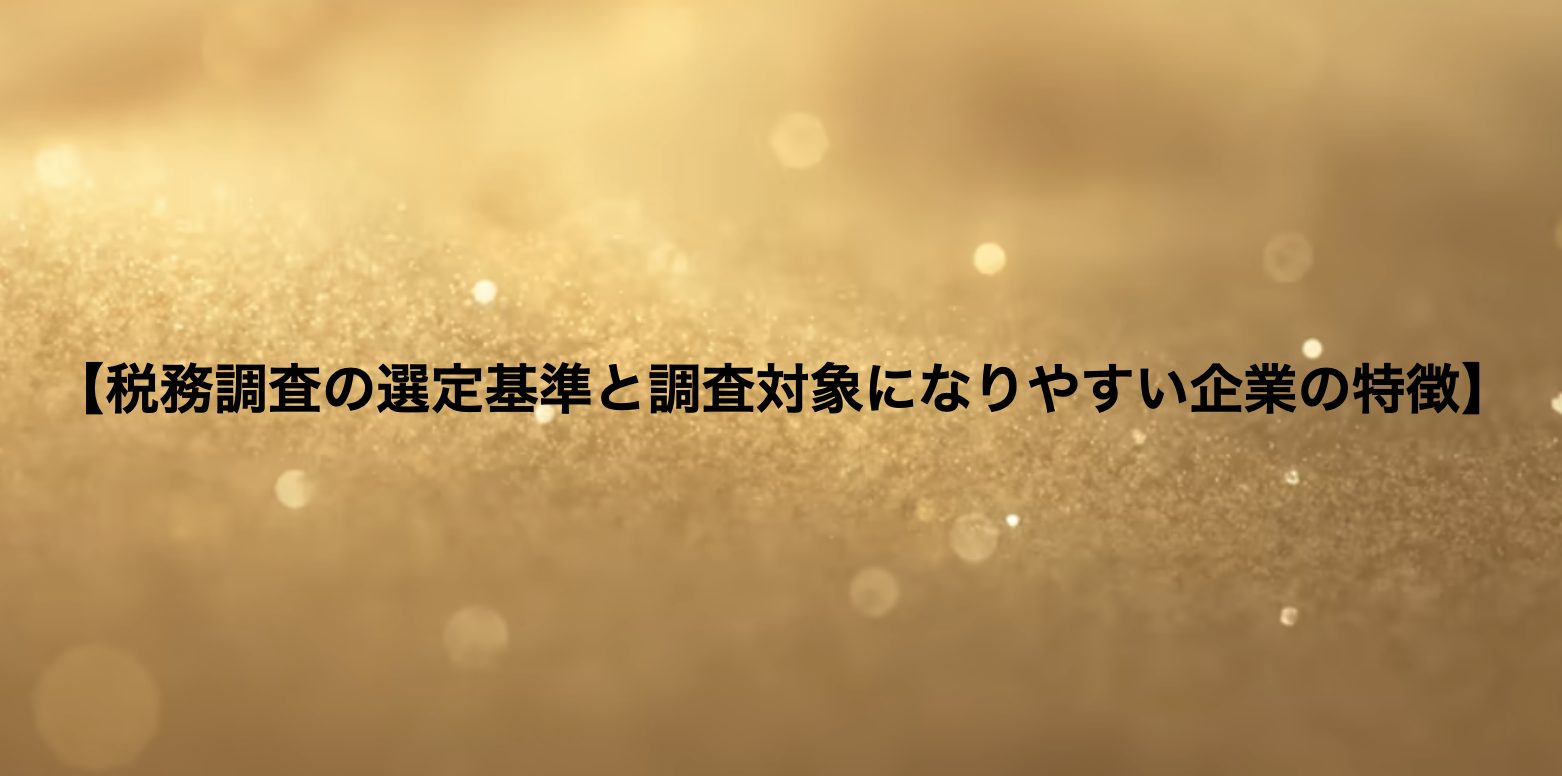

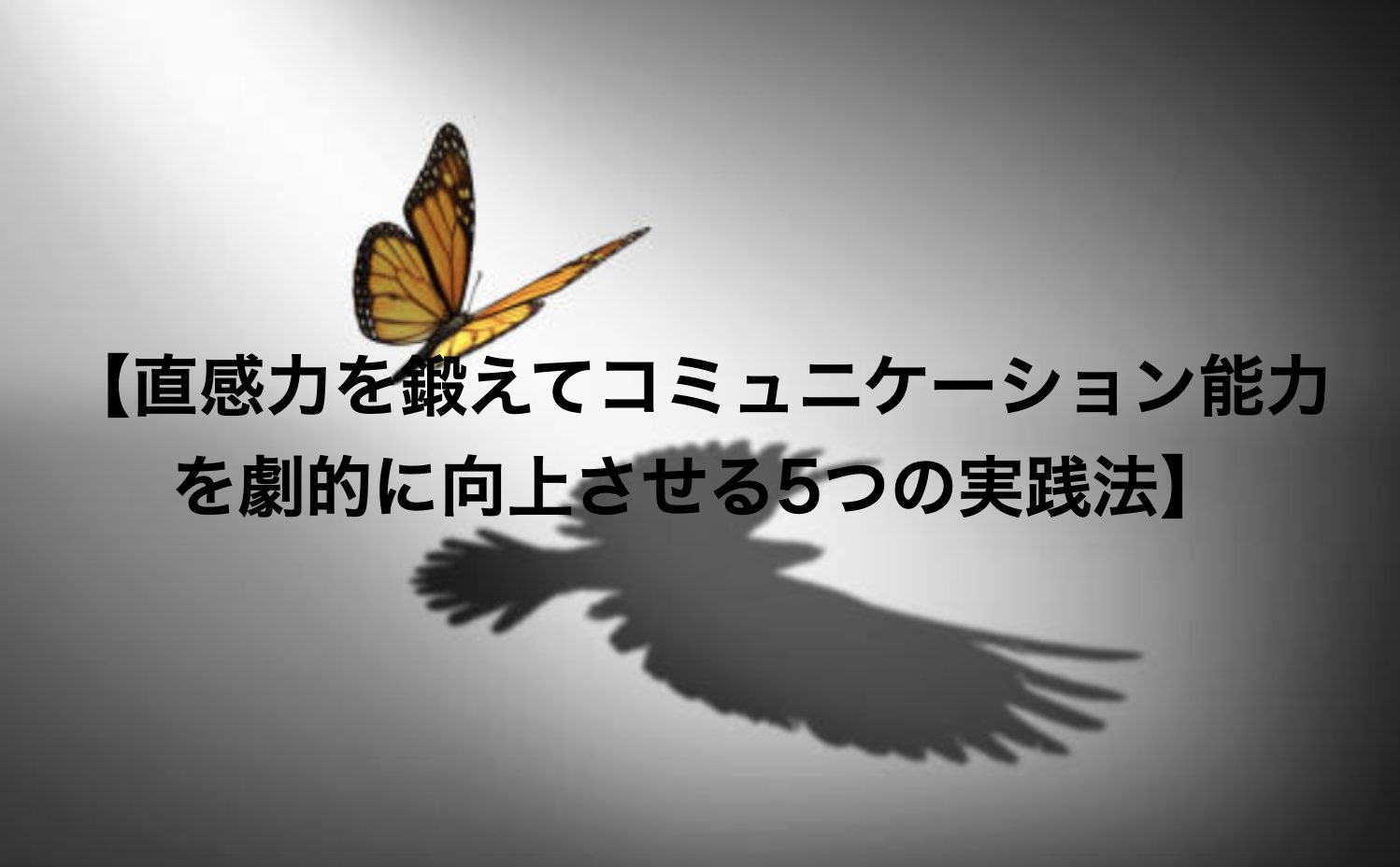
 facebook
facebook LINE
LINE Instagram
Instagram